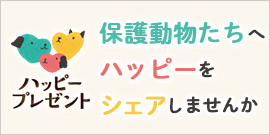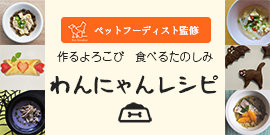- GREEN DOG & CAT
- ペットフード・ペット用品通販
- 犬との生活・特集一覧
- 犬の特集
- 飼い方・生活
- 【第3回】ペットロスと向き合う|愛犬を見送った後の自分の心のためにできること
【第3回】ペットロスと向き合う|愛犬を見送った後の自分の心のためにできること
- 飼い方・生活
- 専門家監修
最愛の親友であり、パートナーであり、子どものような存在でもある愛犬。彼らを失った後の心の痛みや空虚な感じをどうすれば良いのでしょうか。もちろん唯一の正解というものはありませんが、ペットロスがもたらす痛みが強過ぎる時、どんなことが自分の心をサポートしてくれるのか考えてみたいと思います。
※この記事はオウンドメディア「犬のココカラ」に掲載されたガニング亜紀さんの原稿を元に、GREEN DOG & CAT ライフナビ編集部が編集してお届けしています。
愛犬を見送った後の儀式が持つ意味

愛犬を看取った後、悲しみに暮れていても呆然となっていても、手配や手続きをしなくてはいけない事柄があります。小規模とは言え、この点は人間の家族の場合と同じです。
日本では火葬の一連の流れがひとつの儀式になっている場合が多く、ペットの場合も同様です。また、お経をあげていただいてお葬式を執り行うという方も増えているようです。四十九日にペット霊園に納骨をするという方もいるでしょう。愛犬のためにお線香をあげたり、お花を手向けたりといったシンプルな供養や祈りも見送りの儀式のひとつだと言えます。
このような儀式は残された人の心の区切りとして、また気持ちを鎮めるための助けになるとも言われています。手配や手続きなどの実務も心を整理するプロセスの一環です。
私は以前から、日本で犬と暮らしている皆さんが火葬の後のお骨上げまでされていることを羨ましく思っていました。アメリカでは火葬の後に残るのは形が残っていない遺灰です。親族を見送った時と同じように最後にお骨上げができればいいのにとよく考えていました。
ニコの火葬をお願いした会社は、火葬の立会いができるというのも何年も前からそこに決めていた理由のひとつだったのですが、立会いはコロナ禍の影響で叶いませんでした。
とは言え、ニコの身体を引き取りに来てくださった方、後日遺灰を届けてくださった方が、とても丁寧にニコを扱ってくださるのを目にしたことで心が鎮まり「日本式とは違うけれどこれで良かったのだ」と納得することができました。
ニコの遺灰を受け取った日に友人がニコのために贈ってくれた花束が届き、いつもニコが座っていたお気に入りの椅子の隣に遺灰の入った化粧箱とお花を飾って「おかえりニコ」と話しかけた時、心の中でひとつの区切りがついたのを覚えています。
愛犬を喪う悲しみを受け入れて自分の心を守ること

愛犬を喪うことは家族のメンバーを喪うことです。しかし世の中にはペットに対して違う価値観を持っている人もたくさんいます。残念なことに、悲しみの最中にいる時に他の人からの批判やジャッジに直面して傷ついたり、自分自身の悲しみに罪悪感を持ってしまうことすらあります。
ペットロスを専門にしている心理学者は、このような状況について説明をしています。
死というものを恐れる気持ちが強い人の中には、喪失の悲しみに暮れている人を前にした時に非常に心地悪い思いをする場合があります。そのために相手の悲しみをことさらに軽く取り扱ったり、叱咤してしまう人もいます。運悪くそのような経験をしてしまった時に「この人はなぜこんなことを言うのだろう?」と考えるよりも「この人は他者の悲しみに対して軽いパニックになってしまったのかもしれない」と考える方が、ダメージが少なくて済みます。
またペットロスを感じている人も含めて多くの人が、悲しみは一本の時系列の中で時間とともに癒えていくと考えがちです。しかし実際には悲しみは一本の線でもなければ、時系列に沿って消えていくものでもありません。長い間泣けずにいた感情が何ヶ月も経ってから爆発したり、回復したと思っていたのに突然の落ち込みを感じたりするのは珍しいことではありません。ですから「もう何ヶ月も経ったのだから」とか「何年経ってもまだ喪失感があるのはおかしい」と時間軸の中で悲しみを測る必要はないというのが、多くの心理学者が述べるところです。
人間の家族を見送った時よりもペットロスの方が回復に時間がかかることがあるのは「たかがペット」という周囲の声や空気のせいで、自分の悲しみに罪悪感や恥ずかしい気持ちを持ってしまうせいです。可能であれば理解し合えない人とはしばらく距離をおきましょう。誰にでも正直に「ペットロスで落ち込んでいる」と言う必要もないのです。
喪失に対する悲しみは正常で健康な感情です。悲しくて悲しくて胸が痛いのも、ひとりになった時に涙が流れてくるのも正常なのだと受け入れ、きちんと悲しむことは自分の心を守るためにも必要です。
ペットロス、こんな時には助けを求めることも考えて

ペットロスの悲しみの感情は正常なものですが、自分ひとりでは乗り越えられる自信がない、理解してくれる人のサポートが欲しいと思った時には、ペットロスの自助グループに参加したりペットロス専門のカウンセラーに相談するのは良い方法です。悲しみを理解してくれる人と接して話をすることで、深刻なペットロスに陥るリスクを低下させることができます。
もしもその悲しみのせいで身体的、社会的、精神的にマイナスの影響が出て来た時には早急に専門家の助けが必要です。
身体的なマイナス
- 食欲低下で食べないため体重が減ってきた
- 夜眠れない
- 布団から起き上がれない
- 持病の悪化
- 過度の飲酒 など
社会的なマイナス
- 友人との連絡を断ち孤立してしまう
- 仕事を休んだり遅刻してしまう など
精神的なマイナス
- 「生きていても仕方ない」「消えてしまいたい」と感じる
- 自傷行為
- うつ状態 など
上記の他にも、自分自身で「これは深刻だ」と感じることがあれば迷わず助けを求めてください。専門機関を探す気力がなければ、一般の病院で診察を受けて相談することもできます。信頼できる家族や友人がいれば頼んでください。
ペットロスは正常で当たり前の反応ですが、いろいろな条件が重なって深刻に悪化してしまうことも少なくありません。助けや支援を求めることは弱さではなく強さの表れです。
まとめ

実際に愛犬を見送った後の心のケアについて考えてみました。正直に言うと、私自身まだ自分の心と折り合いがつかない部分がたくさんあります。でもこうして書き出したことで整理の目処が立った部分もあります。
また、ここでは「自分の心」と書きましたが、お友達や家族が深刻なペットロスに陥っている時の参考にもなるかと思います。
カウンセリングなどはオンラインで受けられるところが増えており、地域的な障壁やプライバシーの面からもハードルが低くなっています。少しでも必要だと感じたら、専門家に相談することをためらわないでください。
愛犬を喪うのはとてつもなく悲しいことです。けれど犬とのお別れは常に「I LOVE YOU 大好きだよ」で終わります。これは奇跡のように素敵なことだと改めて感じています。
【参考記事】
・What If the Pain of Pet Loss Becomes Too Much to Bear?
<ペットロスと向き合う(全5回)>
・【第1回】ペットロスと向き合う|最愛の犬を見送ることと飼い主の心のケア
・【第2回】ペットロスと向き合う|いつかさよならする時のために今からできる心の準備
・【第3回】ペットロスと向き合う|愛犬を見送った後の自分の心のためにできること
・【第4回】ペットロスと向き合う|子どものペットロス、親は何ができる?
・【最終回】ペットロスと向き合う|仲間を喪った時、残された犬は何を感じる?